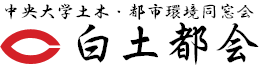1) 研究室紹介
2011年度は,高橋祐幸教育技術員に加えて,M1生が 7名も進学してくれて,大いに活況を呈した年度となりました.夏の引越しも一丸となって対応.学生室のレイアウトが望外にうまくいって,年度後半,石井学部長や学部長補佐の先生方が,外部のお客様をお連れする見学先に選んで下さることもしばしば.白門祭の研究室公開でも前年の学部長賞に続いて優秀賞を受賞しました.バランスよく,テーマも広範にわたるものを,全員がお互いに理解し合って俯瞰的なものの見方を育てるという,研究室の目標については毎年書いていますが,それが理解されているのではと喜んでおります.修論/卒論は研究室のお家芸である「構造信頼性設計」を意識しつつ,震災をどう考えるかが新たなテーマの切り口となりました.ライフラインの信頼性と東北の道路啓開を結びつけたもの(大澤),防波堤の信頼性解析に破壊形態コントロール・避難までつなげたもの(澤田),またソフト系で徒歩帰宅者をへの道路リスク(橋本),原発被害の道路鉄道復旧への影響の経済評価(関川),液状化対策まで考えた耐震補強の費用便益評価(藤澤)など.また地震のからみで,応答加速度とSI値の相関,地域的な特性に対する整理(中北),風のからみで塩害と結びつけたもの(塩野),鉄道の運行規制と結びつけたもの(姉小路).また平野先生のご指導を受けて数値流体解析に挑んだもの(糟谷・鈴木),振動制御と計測(曽根)などのテーマも進行中.
2) 研究室ニュース
上記のように,震災を受けて新しいテーマ展開をはかる年でありましたが,その一方,特に前期においては2年目を迎えた「機能とデザイン演習」に研究室をあげて取り組むことにも,かなりのエネルギーを費やしました.昨年度が試行錯誤であったのに対し,学生として受講した経験者の4年生が教える側に回り,教職員や院生も経験をフィードバック出来てはいますが,白紙の状態の3年生に「創造的」に動くことを伝えるのは,毎年苦心するところ.ただ,研究とは違った意味で,教える側にも得るところの多い経験と理解しています.
佐藤は,2010年刊行の土木学会「土木構造物共通示方書(特にⅡの作用・荷重)の紹介や改善の仕事を続ける一方で,より大きな信頼性設計にもとづく設計ガイドラインの作成作業も土木学会で立ち上げており,性能設計の進展に向けて旗を振る仕事も正念場というところ.それと震災の教訓とは深くかかわる話であって,佐藤にとっては考えることの多い1年となりました.
9月の土木学会全国大会でM1遠田君が優秀発表賞.3月の土木学会関東支部では研究室として18件の発表を実施しましたので,あるいは最多貢献かも知れません.2012年度は進学者6名(ほか1名が他大学へ進学).院生13名は2001年に並ぶタイ記録です.また都市環境学科の名称で入ってきた卒論生が初登場.テーマ選びに変化があるのか,興味津津です.
3) 2011年度卒業生の研究テーマ
○卒研生
|
名 前 |
研究テーマ |
|
姉小路公暢 |
瀬戸大橋線の列車運転規制決定法における各地の風速変化の利用法の検討 |
|
大澤寧子 |
地震時の道路橋被害を想定した道路ネットワークの信頼性評価 |
|
糟谷直樹 |
数値流体解析を用いた円柱まわり流れの解析 |
|
澤田泰希 |
発生頻度を考慮した津波事象に関する防波堤の信頼性解析 |
|
塩野智也 |
構造物にへの飛来塩分量に影響する風のはたらきの定量評価 |
|
鈴木宏之 |
断面辺長比を変化させたときの角柱まわりの流れの検討 |
|
関川翔太 |
福島第一原発事故による自治体の経済的損失と道路・鉄道寸断による影響の調査 |
|
曽根龍太 |
比較的軽量な大型門型柱に対する制振対策方法の検討 |
|
橋本千秋 |
東京都区内における帰宅困難者の交通優先道路の選定 |
|
藤本伸元 |
地震に対する住宅防災投資の妥当性についての検討 |
○大学院修了者(修士)
|
名 前 |
研究テーマ |
|
中北英貴 |
地域ごとの地盤特性が及ぼす加速度とSI値への影響 |